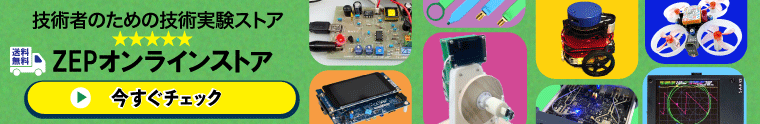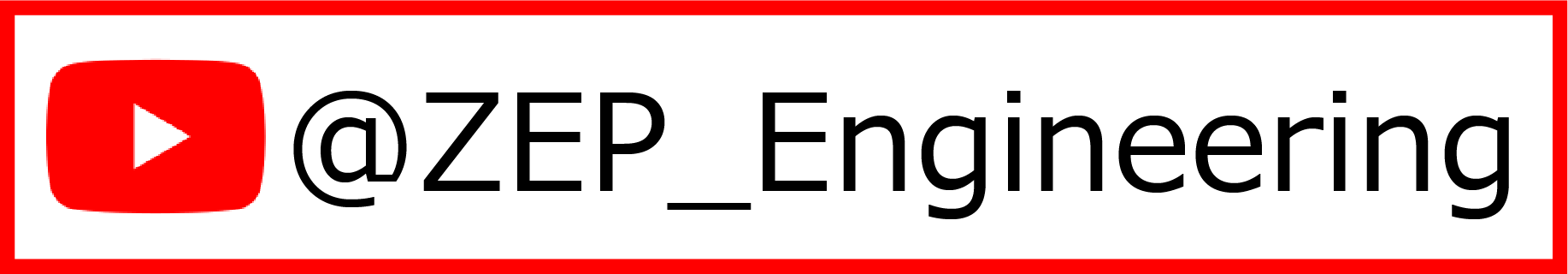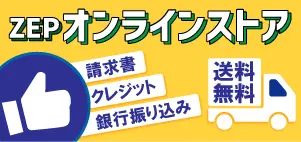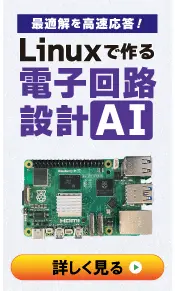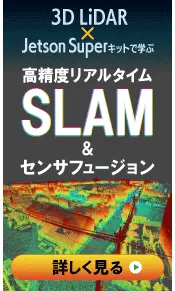[Webinar]プリント基板と電子回路のEMC 実践ノウハウ100
高速ディジタル信号伝送技術から放射ノイズ/静電気対策まで
2025年11月14日

- イベント名:Days on the ZEP 2025 powered by P-ban.com
- 演題:プリント基板と電子回路のEMC 実践ノウハウ100
- 副題:高速ディジタル信号伝送技術から放射ノイズ/静電気対策まで
- 開催日時:
LIVE受講(現地会場):12月19日(金)10:00~18:00
LIVE受講(オンライン):12月19日(金)10:00~16:30
見逃し録画受講:12月20日~12月26日 - 受講方法:現地またはZoomによるオンライン受講
- 会場:
東京都千代田区五番町14 五番町光ビル4F
P板.comセミナールーム
※JR「四ツ谷駅」から徒歩5分 - 受講料:
現地参加:33,000円(税込)/オンライン参加:11,000円(税込)
※本ウェビナ終了後,講義録画と講義テキストを再編集し,書籍付きのVOD(視聴無制限)を発売予定(発売日未定・予価3万~5万円) - 申込締切:12月18日
- 参加者特典:
- 『[PDF]デシベルから始めるプリント基板EMC 即答200』のダウンロード・リンク(全受講者)
- 懇親会ご招待(現地参加者限定)
- P板.com製造サービス 5%/10%割引クーポン(10%割引クーポンは現地参加のみ)
- 主催:株式会社ピーバンドットコム
- 共催・企画:ZEPエンジニアリング株式会社
- 協賛:株式会社システムデザイン研究所
企画趣旨
半導体の高速化・高密度化が進む中で,電子機器のEMC(Electro Magnetic Compatibility:電磁両立性)は重要な設計テーマとなっています.自動車・通信・産業機器・医療機器など,さまざまな分野で高速ディジタル信号による放射ノイズや静電気トラブルが設計品質を左右しています.
本セミナでは,プリント基板と電子回路の電磁界理論から実践対策まで,100のEMC設計ノウハウを解説します.コモンモード発生のしくみ,信号伝送,静電気対策,部品実装技術などについて,第一線の専門家が理論と設計の両面から解説し,次世代エレクトロニクス開発に不可欠なEMC設計の本質を学ぶことができます.〈ZEPエンジニアリング〉
【セッション1】
Todd Hubing教授に学ぶ世界のEMCノウハウ25選
~信号パルスと配線の最大放射電力の考え方~
講師: 櫻井 秋久(株式会社システムデザイン研究所・顧問)

講義内容
セッション1~4は,Todd Hubingの書籍 「EMC Question of the Week (2021-2024)」, 「EMC Question of the Week: 2017-2020」 (日本語版: デシベルから始めるプリント基板EMC, 2023,ZEPエンジニアリング)をベースに構成されています.
書籍では26の技術テーマの元に難易度の異なる約400の質問と解説が与えられています. 本セッションでは特に時間・周波数領域における信号の取り扱い方, 放射エミッション(ディファレンシャル・モード,コモン・モード), デカップリング・キャパシタ,インダクタンスに関するEMC設計・対策の技術向上に必須となるQuestionを取り上げ, 丁寧に解説します.
紹介するノウハウ
- ローカル・キャパシタ:IC直近配置による瞬時電流供給の確保
- グローバル・キャパシタ:基板全体の電源安定化の維持
- キャパシタの並列接続:容量差による共振発生の防止
- 台形波パルスとニー周波数:立ち上がり時間からの高調波帯域推定
- 立ち上がり時間抑制効果:立ち上がり率からn次成分の低減レベルを容易に計算
- デューティ・サイクルの効果:基本波出力最大点の把握
- 高調波の振幅:遷移時間短縮による放射増大の抑制
- スペクトラム拡散:放射ピークの平均化によるノイズ低減
- インダクタンスの考え方:インダクタンスはループ
- 内部インダクタンス:表皮効果で無視
- 外部インダクタンス:いわゆるインダクタンス
- 部分インダクタンス:限られた導体線のインダクタンス,全体を合わせてループ・インダクタンス
- コモン・モード・インダクタンス:信号電流のリターン経路に発生し,コモン・モード電流を誘起するから注意
- コモン・モード放射:キャンセルする電界がない放射
- ディファレンシャル・モード放射:キャンセルする電界があり,通常問題とならない
- 最大放射電力:電流経路短縮による放射強度の低減
- フェライト・コアの効果:放射抵抗をもとに計算
- 寄生発振:異容量並列接続による高Q共振の防止
- 高Q共振:抵抗ダンピングによる狭帯域放射の抑制
- 放射抵抗:アンテナ電流に対応する放射電力を等価抵抗で表わせる(ダイポール72Ω,モノポール36Ω)
- コモン・モード電流:線路の平衡度の違いから発生
- ディファレンシャル・モード電流:ノーマル・モード電流のこと
- 電波暗室での測定:直接波・間接波・アンテナ高さの関係は計算可能
- 偶数高調波:大抵の原因は電源バス
- デカップリング・キャパシタ配置:接続インダクタンス最小化による電源安定化
講師紹介
略歴
- 株式会社システムデザイン・顧問
- 元日本アイ・ビー・エム株式会社技術理事(IBM Distinguished Engineer)
- 技術開発センタ長など
著書
- EMC概論
- EMC概論演習
- ノイズ解決の早道六法
- [Book/pdf]デシベルから始めるプリント基板EMC即答200,ZEPエンジニアリング. https://www.zep.co.jp/asakurai/book/z-emc-bk1/
【セッション2】
理論で本質対策!マクスウェル方程式から始めるEMC対策25選
~電磁界のふるまいを理解して,基板/ケーブル/コネクタを正しく実装~
講師:越地 耕二(株式会社システムデザイン研究所・顧問)

講演内容
EMC問題の解決には,キルヒホッフの法則のほかにマクスウェルの方程式(アンペアの法則,ファラデーの法則)などの知識も必要です. ここでは,同教授書籍の日本語版 「デシベルから始めるプリント基板EMC即答200」 (2023,ZEPエンジニアリング発刊)に沿って, EMC問題解決に必須な電磁気学的な知識や, ケーブル,プリント配線板を含む伝送線路の特性, コモン・モード発生のメカニズムなどの有用な基本的事項について解説します.
紹介するノウハウ
- キルヒホッフの第2法則(電圧則)とマクスウェルの方程式
- キルヒホッフの第1法則(電流則)とマクスウェルの方程式
- 電束密度,磁束密度に関するgaussの法則
- ベクトルの向き/振幅/位相が一目瞭然!電磁界のフェーザ表示
- 完全導体表面では電界の接線成分ゼロ,磁界の垂直成分ゼロ
- 表皮深さを参考にして適切な導体厚を決める
- 高周波磁界は導体内に浸透できない
- 磁流と電流:電磁界の双対性の利用
- アンテナの指向性ゲイン:その定義と等方性アンテナ
- グラウンド面上部における放射界強度:放射波の偏波方向に依存
- 電磁界強度は信号線幅やグラウンド面との距離に依存
- 同軸ケーブルの特性:特性インピーダンスと損失
- 波動インピーダンスは線路形状に依存しない
- 損失が大きいほど,終端インピーダンスの影響を受けにくい
- 周波数や線路長に対して入力インピーダンスは一定に
- 電気長の短い不連続部「コネクタ」のモデリング
- パラレル・ワイア伝送線路の線間距離と伝搬速度
- 平行2線のペアを撚り合わせたときに変化する特性
- 平行2線のペアを撚り合わせると特性インピーダンスは変化するか?
- ワイア・ペアの単位長当たりの抵抗値
- 遷移が伝搬遅延の2~5倍速いなら負荷を整合
- ケーブル終端の回路素子はTDR測定器が示す波形から推定できる
- 誘電体材料が同じでも伝送線路の構造により伝搬速度は異なる
- ディファレンシャル・モード信号がコモン・モード・ノイズに変換される
- ディファレンシャル・モードとコモン・モード間の電圧,電流の関係
講師紹介
略歴
- 1978年3月 東京理科大学大学院博士課程を経て,その後,同大学助手,講師,助教授,教授として奉職,工学博士.
- 2013年4月~2018年3月 東京理科大学嘱託教授
- 2014年6月 東京理科大学名誉教授
- 2018年4月~2021年3月 公立諏訪東京理科大学嘱託教授
- 2020年12月 システムデザイン研究所顧問
- 専門分野は,マイクロ波工学,電波システム工学,電磁環境工学,医用電子工学など.エレクトロニクス実装学会およびライフサポート学会の名誉会員
著書
- 実践講座・共平面形線路入門(1~42回連載),電磁環境工学情報EMC,1992~1996年.
- 電磁駆動型人工心臓,コロナ社,1994年.
- 理工学辞典,日刊工業新聞社,1996年.
- EMC設計技術(基礎編),エレクトロニクス実装学会,2004年.
- プリント回路技術便覧第3版,日刊工業新聞社,2006年.
- EMC概論演習,科学技術出版,2012年.
- [Book/pdf]デシベルから始めるプリント基板EMC即答200,ZEPエンジニアリング,2023年. https://www.zep.co.jp/asakurai/book/z-emc-bk1/
【セッション3】
正しくグラウンディング!間違いだらけの静電気対策25選
~効果的な接地法からシールディングから過電圧保護素子の使い方まで~
講師:藤尾 昇平(日本アイ・ビー・エム株式会社)

講演内容
本講義は,書籍「Todd Hubing教授に学ぶプリント基板のEMC」から 「グラウンド」「シールド」「電磁結合メカニズム」「システムEMC設計」 「静電気放電」「トランジェント保護」に関する設問を抽出・再編したものです.
さまざまなグラウンドの定義と取り扱い方やシステム設計のための注意点, ノイズ結合の考え方,さらにESD(静電気放電)の発生原理と対策の考え方, サージ対策方針など, IT機器の基板・筐体設計者がEMC設計を行ううえで, ぜひとも理解しておくべき重要な内容について解説します.
紹介するノウハウ
- EMCグラウンドの考え方
- 車載機器のグラウンドはシャシー
- 差動信号電流とリターン電流
- フローティング・グラウンドの危険性
- 電源線のグラウンドとは
- 回路基板のグラウンドとは
- 高周波放射ノイズを抑えるグラウンド設計
- ガルバニック絶縁とは直流を遮断すること
- 基板グラウンドは筐体に“直結”が基本
- 接地アース接続だけで放射ノイズはさげられない
- 電圧に比例する容量結合
- マイクロストリップ・ペアのクロストークの原理
- ノイズ電圧に比例するのは電界結合
- LED駆動回路の放射ノイズ対策
- LCDインターフェース・ケーブルは2層フレキが常套手段
- ESD保護には帯電しない袋をつかおう
- 人が歩行して帯電する静電気の極性は
- キーボードのESD対策
- ESD電流のファースト・ピークは分布容量が要因
- ESDは対地容量経由で放電する
- クローバ・デバイスは低消費電力デバイス
- IC入力のESDクローバ・デバイス保護にはTVSと抵抗を使おう
- TVSの特性を理解しよう
- DC入力のTVSは低インダクタンスで接続を
- ユニポーラTVSは電圧しきい値をもつ電圧制限デバイス
講師紹介
略歴
- 1987年 東京工業大学大学院 電気電子工学修士課程修了
- 1987年 日本IBM株式会社 大和研究所入社.IT端末,PC(ThinkPad)などのEMC設計開発, 電磁界シミュレーション解析技術開発,気象データ応用技術開発に従事.
- EMC標準にも携わる.JIEP電磁特性委員会EMCモデリング研究会幹事.
- IEEEシニア・メンバ,iNARTE EMCマスタ・デザイン・エンジニア.
著書
- [Book/pdf]デシベルから始めるプリント基板EMC即答200,ZEPエンジニアリング, https://www.zep.co.jp/asakurai/book/z-emc-bk1/
- 新・回路レベルのEMC設計
- EMC概論
- EMI/EMCのための数値計算モデリング技術
- ノイズ解決の早道六法
- EMC技術特論
【セッション4】
それ都市伝説?目からウロコのEMC対策25選
~パスコン/コネクタの実装からクロックの分配まで~
講師:池田 浩昭(日本航空電子工業株式会社)

講義内容
プリント基板のディジタル回路とアナログ回路の電源は分離した方がよいのでしょうか? 1点グラウンドは本当にEMC対策になるのでしょうか? バイパス・キャパシタのスルー・ホール・ビアは多いほど放射ノイズが減るのでしょうか?
設計者や会社によっても意見が分かれるこれらの疑問について,Hubing先生が簡潔に一刀両断して説明しているノウハウ本があります. 今回はそこから抜粋して,「本当に効くEMC対策」を紹介します.
リターン電流の正しい処理
100 MHzで動作するシングルエンドのアナログ回路と,100 Mbpsで動作するシングルエンドのディジタル回路がある場合,リターン電流は通常どこを通すべきでしょうか? アナログ回路とディジタル回路のグラウンドは分割すべきと言われますが,答えは「同一のグラウンド層」です.
10 MHz以上の周波数では,リターン電流がほとんど配線直下のグラウンドに流れます.したがって,ディジタル回路の配線とアナログ回路の配線を絶縁層厚の数倍離せば,共通インピーダンスによるクロストークの影響はほとんど無視でき,グラウンド・プレーンを分割する必要はありません.
一方,10 kHz以下の低周波では,リターン電流がグラウンド全体に広がるため,共通インピーダンスによるクロストークが無視できなくなります. 例えば,ある回路のリターン電流が1 A,グラウンド・プレーンの抵抗が1 mΩであれば,最大1 mAのクロストーク・ノイズを発生させる可能性があります. このような場合は,グラウンドを分割してアナログ回路専用のリターン・グラウンドを設けた方がよいです.
最適なビアの数
1005サイズのデカップリング・キャパシタを電源プレーンに接続するために用いるビアの数は,各何個が最適でしょうか? 答えは「各1個」です.
高周波では,フットプリントのインダクタンスを少なくすることが重要ですが,1005や1608サイズのパッケージでは,複数のビアを使ってもインダクタンスを下げる効果はありません. 逆にビアを複数実装することで,基板上の貴重なスペースを無駄に占有するデメリットがあります.
雑誌記事やアプリケーション・ノートでは「各フットプリントに複数ビアを使うべき」と主張しているものもありますが,査読付き論文では一貫して「複数ビアを使っても総合的な接続インダクタンスは大きく改善しない」と示されています.
紹介するノウハウ
- CMOSロジックの遷移時間を制御せよ
- グラウンド・プレーンのギャップに着目せよ
- 24層基板の高周波デカップリング・キャパシタ
- デカップリング・キャパシタと電源プレーンの接続用ビアの数
- 差動線路とシングルエンド線路の接続
- マイクロストリップ線路下の銅箔プレーンの電流分布
- キャパシタのさまざまな役割
- コネクタ直下のグラウンドとほかのグラウンドとの正しい接続法
- π型フィルタの最適配置
- フェライト・ビーズの正しい挿入方法
- リターン電流の正しい処理
- サーマル・リリーフ・パッドとインダクタンス
- クロストークとガード・トレース
- クロック信号の分配
- 特性インピーダンスが制御されていない伝送線路
- シャーシが近くにない基板のグラウンド設計
- 同軸ケーブルのシールド法
- 放射が小さいコネクタ実装
- EMC対策の都市伝説
- 100 Mbpsの受信回路の実装
- ベタ・グラウンドに接続してはいけないグラウンド端子
- 100 Mbpsが通過する同軸ケーブルが試験不合格
- 無駄のないスイッチング電源のノイズ対策
- ストリップ線路の間隔とクロストーク
- 整合終端と遠端クロストーク
講師紹介
略歴
- 1994年 東京農工大学 電気電子工学科卒
- 1994年 日本航空電子工業株式会社入社.プリント基板設計,シグナル・インティグリティのシミュレーション業務に従事後, USB-IF,PCI-SIG,VESAなどでコネクタの高速伝送規格化活動に携わりながらノイズ対策業務を行っている.
- iNARTE認定EMCエンジニア,EMCマスタ・デザイン・エンジニア.
著書
- [Book/pdf]デシベルから始めるプリント基板EMC即答200,ZEPエンジニアリング, https://www.zep.co.jp/asakurai/book/z-emc-bk1/
- USB Type-Cのすべて,CQ出版社.
- USB3.2のすべて,CQ出版社.
- 8K映像/USB3.1対応!ケーブル&コネクタ10Gbps伝送技術,CQ出版社.
- 電子回路シミュレータLTspice設計事例大全,CQ出版社.
- IoTのシステムとEMC,電気書院.
- EMC技術特論,科学情報出版.
お問い合わせ
- ZEPエンジニアリング株式会社
- info@zep.co.jp
- 〒177-0041 東京都練馬区石神井町1-23-10 2F(編集室) (03)6325-5451
« 前の記事「[VOD/Semi KIT/data]USBマルチ測定器付き!実測とシミュレーションで学ぶアナログ回路設計」
次の記事「[Webinar/Full KIT/data]復刻!インテル4004プロセッサとビジコン社電卓141-PF」 »